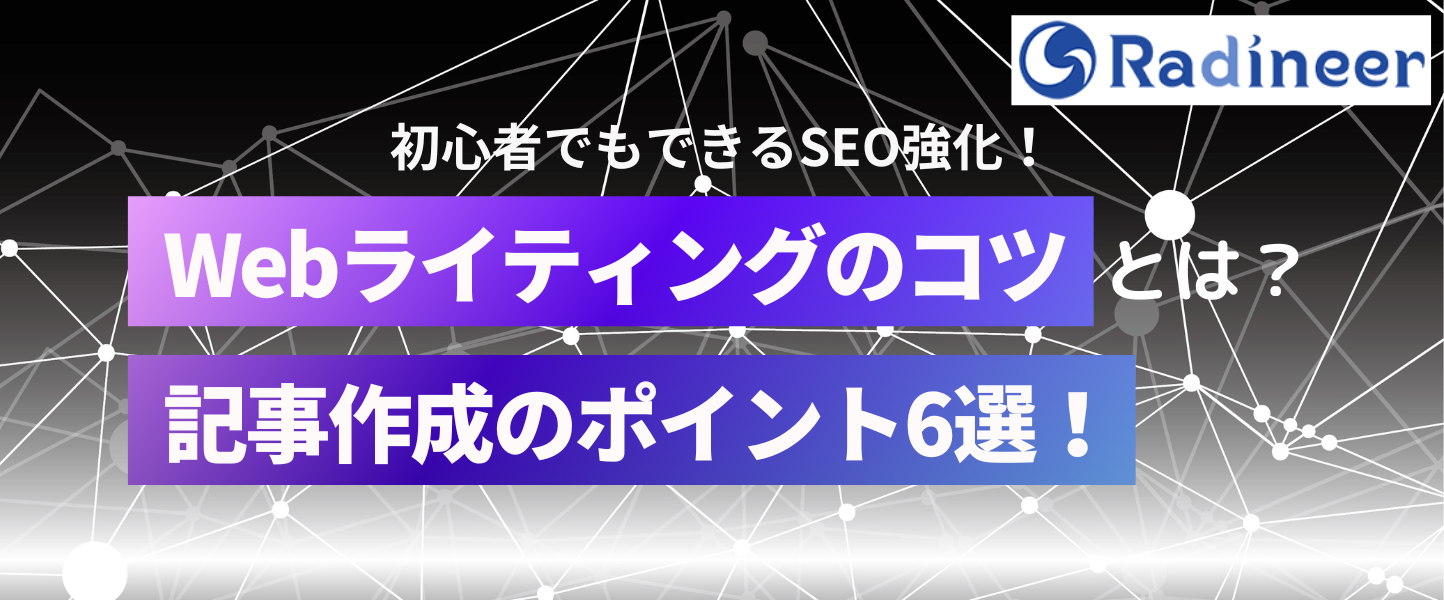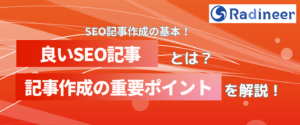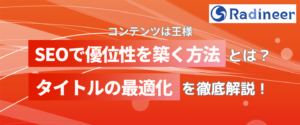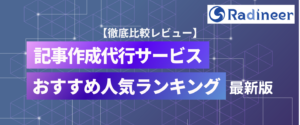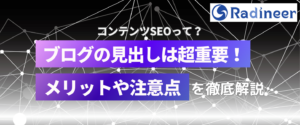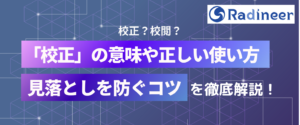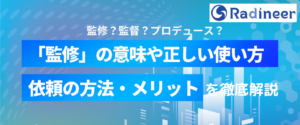今回は、「記事作成のポイント」ということで、
書き方の手順とコツについてお伝えしていきます。
体系的に説明していますので、メモを取りながら読んでもらえるといいと思います!
記事作成のポイント~書き方とコツ~
<手順>
1.キーワード選定
2.検索理由のリサーチ
3.ペルソナの設定
4.構成の作成
5.本文の執筆
6.見直しと修正、リライト
1 キーワード選定
キーワード選定では、まず「テーマ」と「目的」を決めます。
「必要性の高いキーワードの目星を付ける」
「ツールを使って、キーワードの検索数と競合性を調べる」 という事を意識しましょう!
具体的には
・誰に向けた記事なのか…運動不足を気にしている(どのような人に)
・伝えたいメッセージ…ジムに入って健康になろう(どのような情報を届け)
・最終目的…ジムの体験入会を成約させる(どうなってもらいたいのか)
・狙うキーワード…「運動不足 不健康」
といったような感じです!
今回は、「脱毛クリーム」というトピックをキーワードにしていきます!
例にならってみると
・ヒゲや体毛が濃くて気になっているが、「脱毛器・クリーム・エステ(医療・美容)」で迷っている。
・脱毛クリームを使って、念願のツルスベ肌に!
・脱毛クリームのECサイトに誘導し、購入を促す。
・「脱毛クリーム 効果」「脱毛クリーム 永久?」「脱毛クリーム 市販おすすめ」
Google検索などでヒットした上位表示からみると、このようになります!
2 検索理由のリサーチ
…選定したキーワードの関連キーワードを調べます。
→ターゲットがどのような検索キーワードを使って情報を探すのか、
自分が書こうとしている記事にニーズはあるのか、
という点を考えることが大切です!
⇒誤った情報を提供しないように、官公庁やサービスの公式サイトをチェック!
例えば、「脱毛クリーム 永久」「脱毛クリーム 市販」というキーワードから考えると
⑴脱毛クリームで永久脱毛できるのか知りたい
⑵エステとか行かなくても大丈夫?
⑶お店で普通に売ってるの? などが上がってくると思います!
⑴は、「おそらく使ったことがない」 ← 潜在層
⑵は、「どちらにしようか迷っている」 ← 準顕在層
⑶は、「おそらく購入は決めていて、どこで買うか、どれを買うかで迷っている」 ← 顕在層
というニーズ浮かび上がってくるというわけです。
また、客観的にニーズを把握することも大切です。
Googleの検索欄などの上位表示されている5~10記事くらいを確認すれば、
読者が何を求めているかが分かります。
3 ペルソナ設定
ペルソナとは… 商品やサービスの代表的な顧客像のこと
一般的に… ・顧客の心理と行動を理解する
・チーム内での顧客像を統一し、認識の違いを出さない ことを目的とします。
→意識すべきこととしては、「読者の表情が浮かぶくらい詳細にターゲットを設定する」ということです。
実際に設定してみると
名前: 山田太郎
職業・役割: 会社員、営業職
検索の背景:社会人として8年働いているが、毎日のひげ剃りは時間もお金もかかる。若手のころは、フレッシュさでなんとかカバーしてきたが、最近は清潔感という面でも気になってきた。お金がたくさんあれば迷わずサロンに行くが、できれば安く手軽に脱毛を実践したい。
→このように明確に設定すると、情報も正確になると思います。
4 構成を決める
リサーチで分かった「ユーザーが知りたいと思った情報」を「知りたい順番」に並べていきましょう!
また、見出しは、本文の内容を端的に表したものにして、
見出しを読んだだけで、大まかな内容がわかるようにします!
見出しを決めることが出来たら、
読者に最も伝えたい「主張」と、それを支える「根拠」を考えます!
例えば、
主張「脱毛クリームは安くて、カンタンに脱毛できる?」
根拠「脱毛クリームの効果、商品の料金相場など」
主張「脱毛クリームおすすめ3選!」
根拠「ランキング上位の商品3つ取り上げ(通販)など」 などをセットで考えていきます!
本文の構成は、上記から「ストーリー」をつくることが大切です!
流れとしては…
1 仮タイトルを設定し、見出しの候補を選ぶ
2 目的に合わせて伝える順番を決める
3 情報を付け足す・削除するなどしてバランスを整える
4 文章構成として整える
といった感じです!
具体的に説明します。
1 これまでに書き出して考えた「主張」と「根拠」を踏まえて、記事に書かれている内容がすぐにイメージできるような仮タイトルをつけましょう。
そして、仮タイトルを説明するのに必要な情報を、見出し候補として挙げていきます。
それらを情報の階層が判別できるよう、インデントを用いる(文の開始位置をずらす)などして書いていきます。
2 見出しの候補がある程度出揃ったら、それらを並べ変え、目的に合わせて伝える順番を決めていきます。
この際、文章の型(テンプレート)に見出しを当てはめていくと、読みやすく伝わりやすい構成を作ることが容易です。
よく知られた使いやすい文章の型として「逆三角形型」「PREP法」などがあります。
これらは次の章で詳しく解説します。
3 実際に見出しを型に当てはめて並べてみると、情報が不足している箇所、他と比べスケールが小さい・大きい情報、別の
見出しに含まれる情報、重複している情報などが明らかになってきます。
これらの箇所を修正し、新たな見出しをつけてまとめたり、情報を補足・削除したりすることで、全体の情報の流れをスムーズ
にしていきます。
4 最後に再び、情報の階層が分かるようインデントを用いて構成を整えます。その後タイトルや見出しの文言を、実際の記
事で使う、読者にとって魅力的な文言に整えることで文章構成は完成します。
文章構成の段階で自分の伝えたいこと、読者のニーズが反映されていなければ、その後の執筆でいくら良い文章表現をしても、
記事のクオリティを上げることはできません。また、見出しだけ読んでも記事内容がすんなり理解できない、記事を読むことで
得られるメリットなど記事の魅力が伝わっていないように感じるならば、これまでの過程で何かしら問題があったことになりま
す。再度ターゲット設定や読者ニーズ調査、情報収集を進め、構成を再検討しましょう。
5 本文の執筆
記事作成の準備ができたら、いよいよ本文を書きます!
いろいろなサイトで紹介されていますが、本文を書く際は、
「逆三角形型」や「PREP法」などの「型」にあてはめるとよいです!
「逆三角形型」
「結論・最も伝えたいこと」
「具体的な説明・解説」
「補足情報」
「PREP法」
Point(結論)→ まず結論を書く
Reason(理由・根拠)→ 結論に至った根拠
Example(具体例)→ 理由や根拠を補強するため
Point(結論)→ 改めて結論を書く
本文を書く際に意識することは、「一気に書き上げる」ことです!
皆さんも学生時代に携帯ゲームをしながら書いたレポートや、
何か別の作業をしながら読んだ本が進まなかった経験があるのではないでしょうか?
文章を書いているときにいちいち手を止めていると、
その時に考えている余計なことが文章に反映されてしまうので「一気に書く」というのがポイントです!
→文章を書き上げた後に必ず見直し・校正の時間はとると思うので、
まずはどんどん書き進めましょう!
6 見直しと修正、リライト
文章を書き終わったら、見直し・修正を行います!
以下の10項目をチェックしましょう!
| 主語と述語は明確になっているか…「私はサッカー雑誌の記者が本田圭佑がサッカー選手として活躍できた理由を分析した話についてインタビューした。」――このように主語と述語の間が離れすぎていたり、主語と述語の間に別の主語と述語が入ったりしてしまうと、意味を把握しにくい文章になってしまいます。「サッカー選手として本田圭佑が活躍できた理由を分析した話について、私はサッカー雑誌の記者にインタビューした。」などと直せると良いでしょう。 |
| 修飾する言葉・される言葉は近い位置にあるか…「本気で彼はプロサッカー選手になりたいと思っている。」――この場合、「本気で」と「思っている」が離れてしまっているために修飾関係が分かりづらくなってしまっています。「彼はプロサッカー選手になりたいと本気で思っている。」のように少し単語の位置を見直すだけで読みやすくなります。 |
| 読点(、)を正しく使えているか…読点の使い方に正確な規定はありません。しかし、多すぎると意味が細切れになってしまい、少なすぎると語と語の関係が分かりづらくなります。読点を打つかどうか迷う場合は一度ゆっくりと音読し、間を設けた方が自然な箇所には読点を入れるようにすると良いでしょう。外部サイト(https://apj.aidem.co.jp/column/78/)によると、「主語の後に打つ」「文と文を分けるところに打つ」「並列関係にある語句の後に打つ」「修飾語がどこにかかるかわかるところにうつ」「接続詞の後にうつ」など様々なルールがあるそうなので、参考にしてみてください。 |
| トンマナを統一できているか…トンマナとはトーン&マナーの略で、企業などで文章作成やデザインなどを行う時のために、表現のルールを定めているものです。使う言葉や表現に統一性を持たせ、読み手がその企業に持つ印象が制作物によって変わらないようにする目的があります。記事作成では、文体は企業の持つ(狙う)雰囲気に合っているか、用語や表記の揺れが生じていないか、表現の硬さ・柔らかさなどがチェックポイントになります。 |
| 文章のリズムを整えられているか…「〜です。〜です。〜です。」など同一の文末表現が続いると、文章のリズムが単調になってしまいます。凝った技法は必要ありませんが、前後の表現と変化をつけるようにしましょう。また、一つの文に複数の情報が入り、長すぎるのも読みづらくなる原因です。40字〜70字程度に収まるように調整しましょう。 |
| 誤字脱字は含まれていないか…誤字脱字のチェック方法として、Microsoft Wordなどのスペルチェック・校閲機能を使う方法、印刷してチェックする方法などがあります。自力でチェックをする際は、文章を読み取ろうとするのではなく、文字・単語・固有名詞を一つずつ確認していくと良いでしょう。文章として読んでしまうと、内容を理解している筆者では脳が文章に補正をかけてしまい、誤りに気づきにくくなってしまいます。 |
| 漢字とひらがなのバランスは適切か…「漢字3割、平仮名7割」をおおよその目安にしましょう。それよりも漢字の割合が多くなると読みにくくなったり、堅苦しい印象になったりします。例えば「有難い」を「ありがたい」、「失礼致します」を「失礼いたします」など、平仮名で書くことで読みやすくできますね。 |
| 漠然とした表現を多用していないか…情報を提供する記事である以上、曖昧な表現は避けるべきでしょう。例えば「30代女性のほとんどが買っている」という文では、「ほとんど」の表すボリューム感が人によって異なるため、記事の信頼性に疑問を持たれかねません。このような場合は「およそ○割」など、具体的な表現に変えていく必要があります。 |
魅力的なタイトル・リード文になっていないか…タイトルは読者が最初に読む文言です。読者はタイトルを読み、その記事を読むかどうかを判断します。タイトル作りでは以下の3点を押さえましょう。
タイトルを見て記事に興味を持った読者は、リード文を読み進めながら、改めて「記事を読むかどうか」を判断しています。リード文では記事の方向性を明らかにしつつ、興味を誘って本文へとうまくつないでいきましょう。あくまで導入なので、あまり長くなりすぎないよう注意します。 タイトルを見て記事に興味を持った読者は、リード文を読み進めながら、改めて「記事を読むかどうか」を判断しています。リード文では記事の方向性を明らかにしつつ、興味を誘って本文へとうまくつないでいきましょう。あくまで導入なので、あまり長くなりすぎないよう注意します。 |
| 改行を正しく使えているか…改行によって生まれる文章の一まとまりが段落です。一つの段落で一つの話題を扱うようにすることで、読みやすい記事になります。最近はPCやタブレット、スマーフォンなど記事を閲覧するブラウザが多様化しており、改行を多用するとスマートフォンなど小さい画面で閲覧した際に読みにくくなります。適切な位置で改行を入れることと、段落にある程度のボリュームを持たせることを意識しましょう。 |
続いては、記事作成の「コツ」をお伝えします!
列挙していくので、参考にしてください!
・適度に改行する
…記事の本文は3~4行を目安に改行しましょう。
同じ内容でも改行の有無によって読みやすさがまったく異なります。
とくに漢字の多い文章や専門的な内容の場合、改行がなく文章が続くと読みづらく、離脱の原因となります。
また、一文が長くなりすぎないよう気を付けましょう。一文が長くなると句点が多くなると主語と述語の関係が変わってしまう「ねじれ」も起きやすくなります。
・同じ語尾を続けて使わない
…同じ語尾が続くと、読みづらく、稚拙な印象となるため避けるようにしましょう。
脱毛クリームには「つけ心地がよい」「肌がつるつるになる」「手軽に安くできる」という3つの特徴があります。
素手でも、付属のパーツでもきれいに塗ることが出来ます。脱毛した後もカミソリで剃った後とは違ってつるつるな肌を実現します。
また、脱毛器やカミソリ、エステと比べて手軽に安く脱毛ができます。
上記のように語尾がすべて「ます」で終わっていると、リズムが悪く読みづらいと感じないでしょうか。
語尾を変えた文章と比べてみてください。
脱毛クリームには「つけ心地がよい」「肌がつるつるになる」「手軽に安くできる」という3つの特徴があります。
素手でも、付属のパーツでもきれいに塗ることが出来、脱毛した後もカミソリで剃った後とは違ってつるつるな肌を実現できるのです。
また、脱毛器やカミソリ、エステと比べて手軽に安く脱毛ができます。
一文の長さを調整し、間の語尾を一つ変えるだけでも読みやすさが違ってきます。
・次に何をすればいいのかを提示する
…ユーザーの行動を促すためには、ユーザーが次にとるべき行動を提示することが大切です。
ユーザーが情報を得て満足してブラウザを閉じてしまわないように、記事作成の目的に沿って次の行動を提示しましょう。
非常に単純ですが、意外とできていないことの多いポイントです。
せっかく上位表示されても次にとるべき行動がわからない記事であれば、ユーザーは離脱してしまいます。
リンクをボタン化してわかりやすく表示する、適切なタイミングで内部リンクを入れる、誘導文を入れるなど、記事内で次の行動につなげる動線を作りましょう。
・論理の飛躍を起こさない
※ この項目は説明します!
ex) 日本は少子化が進んでいる。認定こども園を増やすべきだ。
この文は、意見としては正しいかもしれませんが、もう一つ二つ根拠を挟む必要があります。
例えば、「待機児童問題を解決するため」や「子育ての選択肢を広げることができる」などです。
・ねじれ文を書かない
※ この項目も説明します!
ex) 「今日の晩御飯は、カレーを作りました。」「鈴木くんの志望校は、Ⅿ大学に合格しました。」
などの主述がずれている文を指します。
・記事入力効率化ツールを使う
…ツールを利用することでも、記事作成にかかる時間は短縮できます。
記事作成は、機械にやってもらった方がより早く正確になるフェーズが多いのです。
代表的なものだと、よくつかうワードの辞書登録などが挙げられます。
その他にも、以下のようなツールは記事作成の仕事でよく利用されていますね。
- Google Documentの自動変換機能
- テキスト編集ソフトの置換機能
- 読み上げ機能による校正作業の効率化
自分に合ったツールを利用して執筆を効率化してみてください!
7 まとめ
いかがでしたでしょうか?
とにかく大事なのは、「記事」は「読者」に伝えるものだということです。
自分自身が読み手になったつもりで、思わず読んでしまうような文章を書くことを意識しましょう!
参照文献:
https://www.craudia.com/crarepo/archives/1646
https://nexer.co.jp/weiv/writing/
https://yosca.jp/technique/3234/
フリーランスや在宅で働きたい方、副業・キャリアアップを考えている方には、株式会社日本デザインの短期のオンラインスクールがおすすめです。
「WEBデザイン」「WEBライティング」「動画編集」「プログラミング」などの習得を支援し、誰もが理想の働き方を実現できるようサポートしています。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
日本デザイン|ライティングの知りたい!知りたかった!が見つかる情報サイト